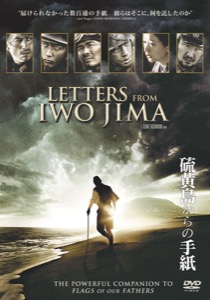当コラムはURBAN RESEARCH MEDIAにて掲載された内容です。
文中に登場する作品
1
「プライベート・ライアン」
冒頭30分にわたるノルマンディー上陸作戦の衝撃。
プライベート・ライアン
http://db2.nbcuni.co.jp/contents/hp0002/list.php?CNo=2&AgentProCon=38889&SP=2
SAVING PRIVATE RYAN
2
「硫黄島からの手紙/父親たちの星条旗」
硫黄島の戦いを日米双方から描く。
硫黄島からの手紙
https://warnerbros.co.jp/home_entertainment/detail.php?title_id=2176
Letters from Iwo Jima
父親たちの星条旗
https://warnerbros.co.jp/home_entertainment/detail.php?title_id=2175
Flags of Our Fathers (BD)
さて、映画にはアクション、コメディ、サスペンス、スリラーなど様々なタイプがあるが、中でも「戦争」を題材にした作品群は大作も多く、シネマの一大勢力といっていいだろう。戦争シーンのスペクタルやサウンドをフルで堪能し、大迫力を味わうという意味では映画館で観るのに最も適したジャンルかもしれない。
今回もいつもどおり3本のタイトルを挙げた(実際には4本だが、後述します)。どれもお気に入りの素晴らしい作品だ。これらの作品は共通して第二次世界大戦を舞台にしているが、作られた年代は1990年代、00年代、10年代とバラバラだ。
ではなぜ数ある戦争映画の中で僕はこの3作品をピックアップしたのだろう?いずれも名作の呼び名高いが、世間での評価とは当然として、僕自身の考える「いい戦争映画の条件」について、自らの価値観を掘り下げながら分析してみたい。
1.「プライベート・ライアン」
スティーブン・スピルバーグがアメリカ軍によるフランス領侵攻「ノルマンディー上陸作戦」を描き、アカデミー賞5部門受賞した映画史に燦然と輝く言わずと知れた”超”名作だ。とある家族の4人兄弟のうち3人が戦死したとの報告を受けたアメリカ陸軍参謀総長が、万が一兄弟全員が戦死とあっては厭戦ムードを加熱させかねない、と懸念し「末っ子のライアンを本国に送還するため見つけ出せ」と現地に司令を出す。兵士たちは自分たちの命もどうなるかわからない状態で名前だけを頼りに命がけでライアンを探し出すことになる。戦地から他人の命を救うために。

特に圧巻なのはD-デイ侵攻作戦と呼ばれる冒頭24分のオマハビーチを舞台にした戦闘シーン。巡航ミサイルも誘導弾も、もちろんドローンだって存在しない世界で、これでもかというぐらい凄惨な銃撃シーンが続き、海岸が米兵の血で染まる。銃撃シーン、と言っても急勾配の海岸線の上から攻撃を仕掛けるドイツ軍はほとんど描かれず、何が起こっているのかも理解できないまま仲間たちが倒れていく。そもそも映画を観る側はまだ誰が主人公かも分からず、画面に映った回数やセリフの量で「この兵士がメインキャラかな?」と思い感情移入するが、その直後に当人が頭を撃ち抜かれて死んでしまうような有様だ。いわゆる「死亡フラグ」のようなセリフもなければ、家族に遺言を伝える時間も与えられない。瞬殺だ。
撮影には特殊に加工したカメラが使われた。手揺れなどを極力排したドキュメンタリーチックなレスポンスの速い映像。画質はフィルムの豊かさを保ちつつ、まるでスマホの60fps撮影のようなキビキビした躍動感を兼ね備えている。当時としては画期的な手法だ。
撮影に参加した役者たちは絵コンテなどを渡されず、言われるがままに次々と海へ飛び込み、上陸していったという。撮影現場は混乱したが、その混乱と無秩序こそがスピルバーグの表現したい戦場というものだったのかもしれない。
何よりすごいのはそのゴア描写(グロテスクな表現)だ。B級ホラーでもやらないレベルの出血表現、人体欠損、肉体破壊をこれでもかと並べ立てる。その「殺られるシーン」が実際に死体となってスクリーンに積み重なり、時間経過と共に観ている側も、もう慣れるしか術がない。人体としての機能や体温、重量感を感じさせるそれらの「屍」は観るものに否が応でも戦争の悲惨さを伝える。僕はこれを非常に重要だと考えている。戦争とは結局のところ「人体を破壊する行為」であるということを思い知らせてくれるからだ。
これは僕の考える「良い戦争映画」の条件のひとつ。
「腸がはみでる」
そんなまとめ方あるか?と思うかもしれないが、今まで戦争映画を観てきたひとつの基準として、この「腸がはみでる」という表現に踏み込むかどうかはひとつの個人的な試金石となっている。これは戦争に対する警告であると同時に、映画に対して僕が期待している「ヴァイオレンスなものが観たい」という欲望も叶えてくれる。このアンビヴァレンスな感情を自覚することも戦争映画を語る上で重要だと思う。自分の中にある決して自身では発露できない暴力に対する憧れのようなものだ。
2.「硫黄島からの手紙/父親たちの星条旗」
こちらもスピルバーグに負けない巨匠クリント・イーストウッドによる、小笠原諸島で起こった日米の戦闘”硫黄島の戦い”を描いた連作。
「硫黄島からの手紙」は日本側からの視点として、栗林忠道陸軍大将指揮を主人公に、敗戦濃厚な戦況下で故郷を想いながらどうにか生き抜こうとした日本兵たちの内面が描かれる。主人公の渡辺謙はもちろんだが、あらたに映画のために創作された青年兵西郷を嵐の二宮和也が演じたことでも話題になった。勇ましさからは程遠いパン屋の青年をまさに人気絶頂のアイドルが演じたことに意味があるといえる。

本作は大部分を軍内部でのやりとりが占めており、勝つか負けるかの銃撃シーンがほとんど存在しない。印象的な銃殺シーンのほとんどは逃走中に背後から(しかも自国の上官から!)、あるいは投降した敵国の兵士に無抵抗な状態で、など、戦争における「英雄」の死に様からは程遠い殺され方をする。しかしそれでもまだ物語としてスクリーンに映すには十分にドラマチック、作画的と言えるだろう。アジア太平洋戦争における日本人の死因は餓死がトップで過半数を超えているという研究もある。その次がマラリアなどの病死。映画の中に限っていえば鉛を受けてリアクションしながら死ねるだけマシだ、という気もしてくる。
正直「硫黄島からの手紙」の内容だけを観れば凡庸とは言わないまでも数ある名作のひとつという印象だ。海外経験もあり素養もある中将の先進的(すなわち現代的)な判断力とカリスマ性、それを妬んでか横暴を働き軍を無謀な作戦に巻き込んでいく古参将校、そして戦場に駆り出され、巻き込まれる温厚な青年。今までの反戦的なテーマの映画にありがちなストーリーといえなくもない。
しかしクリント・イーストウッドがすごいのはこの戦いをアメリカ側の視点からも描いた作品をほぼ同じタイミング(公開の間隔が2ヶ月!)で完成させたことだ。
「父親たちの星条旗」は同じく“硫黄島の戦い”が大量の犠牲を出しながらも辛勝した米軍側の視点から語られる。勝利のシンボルとも言える摺鉢山に星条旗を掲げた “記念写真”はアメリカ全土に広まり、そこに映る兵士たちは英雄としてメディアに取り上げられた。しかしその写真が撮られた背景にはある秘密があり、戦争時に死んでいった仲間たちの記憶と相まって、英雄たちを苦しめる。その“生き残った英雄たち”が主人公になる。
彼らは戦場で地獄を経験しただけでなく、為政者によって真実とはかけ離れた勝利の象徴として扱われ、戦争が終わったあとも二重の苦しみを味わうことになる。
戦争におけるすべての兵士には被害者的な側面が必ずある、という事実を描くのは重要だと思う。「すべての」というのはつまり、敵国の兵士もまた人間である、ということだ。それには戦勝国も戦敗国も関係ないだろう。「硫黄島プロジェクト」と呼ばれるこの2作をひとりで撮ったクリント・イーストウッドの創作意欲には本当に驚かされる。しかも「硫黄島からの手紙」はそのほとんどを日本人キャストで撮影しており、監督本人も「日本映画だ」というほどだ。
惜しむらくはこれらが結局は独立した2本の作品になってしまったことだろう。あえて強い言い方をすれば2作に分断されてしまった、とも言える。映画自体を二部構成にするのか、平行して描くのか、この2作がもし1つの作品だったとしたら、より強度の高い作品になったのでは、と思う。片方だけでは結局どちらも観てないのと変わらない。是非2作合わせて観ることをお薦めします。
ということで個人的「良い戦争映画」の条件ふたつめ。
「双方の国の兵士の被害者的側面が描かれる」
どう?これは、あまり異論はないでしょう?
3.「この世界の片隅に」
こうの史代の同名漫画を原作に、広島と呉を舞台とした戦時の市民たちを描いたアニメーション作品。片渕須直監督はクラウドファウンディングで資金を集め本作を完成させた。主人公すずの声をのん(能年玲奈)が務めたことでも話題になった。現在さらにキャラクターとシーンを多数追加した「この世界の(さらにいくつもの)片隅に」が公開中だ。
僕は公開前に試写会で鑑賞させていただいたのだが、そのあまりの描写とメッセージ性に、帰り道の平和な東京を歩いてるだけで泣けてしまったことをよく覚えている。そのままその年の個人的年間ベスト1に選んだ人生でも強く心に残る一本だ。
主人公すずの少女時代から結婚を通して、当時のリアルな生活や価値観が自然と伝わってくる。現代の視点からジェンダーや男女の不平等、人権という目線でみると本当にひどい時代だな、と正直思うが、それでもその常識の中でお互いを思いやる人々のやりとりが魅力的だ。戦時下で物資がどんどん不足していく中、貧しいながらも限られた食材を使って料理をつくる女性たち。その描写が細かくて観ているだけでこっちのお腹が空いてくるのがおかしい。
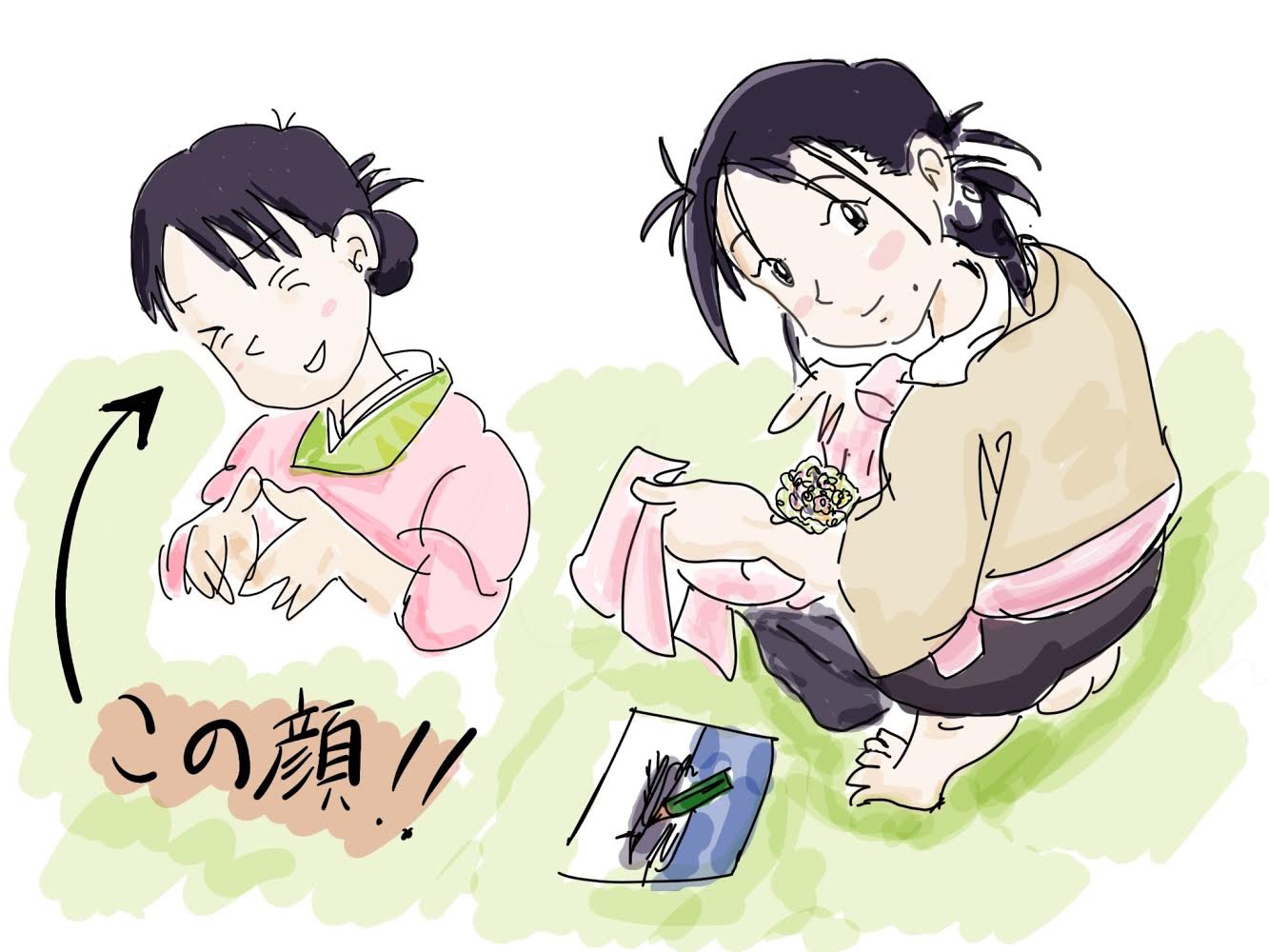
だがその人々が「やれやれ」と言いつつ現状を受け入れてる様子が現代の自分たちと重なり怖くもあるのだ。実際、「多少の不便」程度の描写で描かれる本作の中の戦争はある時点で突然凶暴な牙を剥く。「戦争中も人の生活があったんだなあ」などとのどかな気持ちで観ていたこちら側の心臓を突き刺すインパクトは今回とりあげた他の作品にもまったく負けていないだろう。
この映画で恐ろしいのは戦争や死、暴力といったものが普段の生活と地続きで、ゆっくり侵食してくる、ということだ。それらは生活を埋め尽くしたときにはもう手遅れで、あとはランダムに好きな場所で爆発する。まるで時限装置のついた地雷のように。こちらは恐怖に怯えながらも普通に生活を続けるしかない。
ただ「この世界の片隅に」はその絶望の先で、遺された者の希望もちゃんと描いてくれる。悲惨な風景に破壊された心にそれが暖かく流れ込み、すこし冷えて固まった頃にちょうど映画は終わりを迎える。
あ、ダメだ。思い出したら泣いちゃう。
「良い戦争映画」の条件みっつめ。
「戦争は日常の延長にあることを教えてくれる」
日本人がSNSで自国の戦況について呑気に議論する未来だってありえるかもしれない。警戒心だけは持っていたいものだ。
というわけで「良い戦争映画の条件」と掲げておきながら、自分自身の思想を色濃く打ち出す結果となってしまった。本来こんなことを書いてもあまりいいことはないのだ。まあでも「生活と映画」ですからね。タイトルに忠実に書いたらこうなった、という感じ。
しかしこの3つの条件「腸がはみでる」「両国の兵士を描く」「日常の延長にある」をすべて兼ね備えたところで果たして良い映画になるのだろうか。どうにも説教くさいつまらない作品になりそうだ。結局のところ英雄や暴力やときにお色気描写だって必要だろう。
大事なのは「戦争は映画の中だけでもう十分」と僕たちに教えてくれることだ。